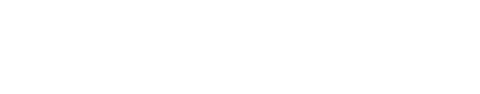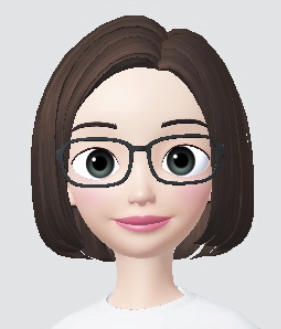どれも「物を作ること」という意味ですが、何を/どうやって作るかがちがいます。
では、くわしく見ていきましょう。
Contents
「制作」「製作」「作製」「作成」の意味のちがいと使い方
それぞれのちがいを表にまとめてみました。
|
|
何を/どうやって作るか |
|
制作(せいさく) |
芸術作品や映画やテレビなどの番組を作る。 |
|
製作(せいさく) |
道具や機械を使って作る。型に合わせて作る。 |
|
作製(さくせい) |
品物や機械、図面を作る。 |
|
作成(さくせい) |
書類や文書を作る。 |
ひとつずつくわしく説明していきますね。
制作の意味と使い方
まず、辞書で意味を調べてみましょう。
制作:
1.定め作ること。考え定めること。また、そのもの。
2.詩歌や物語を作ること。
3.絵画、彫刻などの作品を作ること。
4.映画、演劇で、作品を作り上映、上演すること。プロデュース。
出典:日本国語大辞典:
「制作」は、絵や彫刻などの芸術作品や、物語や番組などを作るときに使う言葉です。
絵、物語、音楽、番組など、どれも作る時にはクリエイティブな力が必要です。
クリエイティブというのは、日本語では創造的(そうぞうてき)とか独創的(どくそうてき)と言います。ほかの人のまねではなくて、それを作る人だけが持っているアイディアやセンスを使って作る力という意味です。
何もないところから、自分のアイディアや自分だけの考を使って、形になるものを作ることが「制作」です。
音楽や番組は一人だけで作ることは難しいですから、何人かが協力して作る場合にも「制作」を使います。
使い方の例を見てみましょう。
・テレビの制作会社で働いています。
・制作中の絵を見せてくれました。
・壁に巨大なアートを制作した。

製作の意味と使い方
では、次に「製作」の意味を辞書で調べてみましょう。
製作:
道具・機械などを使って型にはまった物を(大量に)作ること。
また、その道具・機械を作ること。
出典:新明解国語辞典:
ポイントは「道具・機械」のところです。
例えば、絵は絵の具と筆と紙があれば作ることができます。でも、「製作」の場合は、もっとたくさんの道具が必要だったり、大きな機械が必要だったりします。
例文を見ると、もっとわかりやすくなると思います。
・家具の製作を頼んだ。
・飛行機の製作が進んでいる。
・中村製作所はロケットの部品を作っている。
「家具」も「飛行機」も「ロケットの部品」も少ない道具では作れませんよね。たぶん大きな機械も必要だと思います。ですから、「製作」を使います。
辞書の意味の中に「型にはまった物」とありますが、これも重要です。
「型にはまった」というのは、決まった形や方法があって、その通りにするという意味です。クリエイティブの反対のような言葉ですね。
「製作」は、決められた形や方法に合わせてものを作るという意味もあります。
例文の「家具」「飛行機」「ロボット」は、作り方の設計図があって、それに合わせて作りますよね。それに合わせないで作ると、飛行機は飛ばなくなってしまいますよね。だから、「製作」を使います。
作製の意味と使い方
次は、「作製」です。意味を辞書で見ておきましょう。
作製:ものをつくること。製作。
出典:広辞苑:
作製:品物、機械、あるいは図面を作ることをいう。
出典:使い方の分かる類語例解辞典:
広辞苑では「製作」と同じ意味ということになっています。「製作」と「作製」は漢字の順番が違うだけですから、意味も似ています。
でも、少し違うのは、「製作」は道具や機械を使って何かを作りますが、「作製」は、道具や機械を作るということです。
つまり、「製作」のために必要になる物を作るのが「作製」です。
使い方の例を見てみましょう。
・家の設計図を作製する。
・ダムを製作するための基本計画を作製した。
「設計図」は、家を作るときのもとになるものですよね。だから「作製」を使います。
「基本計画」もダムを作る前に作られるものですから「作製」を使います。
また、「作製」は「製作」よりも小さいものを作るときに使われることもあります。
・人工衛星の写真をもとに地図を作製した。
・作製されたポスターが駅に貼られていた。


作成の意味と使い方
では、最後に「作成」の意味と使い方を確認しましょう。
まずは、辞書の意味です。
作成:計画や書類、また文章などを作ること。
出典:大辞泉:
「作成」は、書類や文書を作るときに使う言葉です。
例文を見てみましょう。
・報告書を作成する。
・新聞記者が作成した記事が取り上げられた。
・作成した計画がダメになってしまった。

では、さっき「作製」のところででてきた例文で「作成」は使えるでしょうか。
〇人工衛星の写真をもとに地図を作製した。
△人工衛星の写真をもとに地図を作成した。
「作成」は、「作製」より規模が小さい物や量が少ない物を作るときに使われます。
人工衛星の写真をもとにして地図を作ることは、大きなプロジェクトなので「作成」はぴったりではありません。例えば、「夏休みの宿題で地図を作成した。」だったら、「作製」ではなくて「作成」がぴったりです。
〇作製されたポスターが駅に貼られていた。
△作成れたポスターが駅に貼られていた。
駅に貼られるようなポスターですから、どこかの会社がたくさん作ったものだと思います。この場合は、「作成」ではなく「作製」のほうがぴったりです。「美術の授業でポスターを作成した。」だったら、「作成」がいいと思います。
もし「ポスター」が、プロのデザイナーがクリエイティブな力を使って作った芸術的なものだったら「制作」のほうがいい場合もあります。
同じポスターでも、どのように作られたかでどの言葉がいいかが変わってきます。
「制作」「製作」「作製」「作成」のちがい、まとめ
「制作」「製作」「作製」「作成」のちがいは、わかりましたか。何を/どうやって作るのかを考えて、使い分けてくださいね。 最後にもう一度使い分けのポイントを書いておきます。
|
|
何を/どうやって作るか |
|
制作(せいさく) |
芸術作品や映画やテレビなどの番組を作る。 |
|
製作(せいさく) |
道具や機械を使って作る。型に合わせて作る。 |
|
作製(さくせい) |
品物や機械、図面を作る。 |
|
作成(さくせい) |
書類や文書を作る。 |
日本語Q&Aへの質問やコメントはこちらから
日本語を勉強していてわからないことがあったら、以下から質問してください。だいたい2週間くらいで、このホームページでお答えします。